
法隆寺まで走って行って、参拝せずに、走って帰る。
今日はどこまで走ろうかと考えて、法隆寺に決めた。 googlemapで距離を見ると片道13〜4Kmほどなので ちょうど良いかもしれない。 前回の談山神社ではあまりにも坂がキツかったが 今回...
No time like the present!!

今日はどこまで走ろうかと考えて、法隆寺に決めた。 googlemapで距離を見ると片道13〜4Kmほどなので ちょうど良いかもしれない。 前回の談山神社ではあまりにも坂がキツかったが 今回...
![[春秋要約161126]北方領土問題に世論が必要だが、日本人の「問題」と地元の「出来事」では意識が異なる。<40文字> #sjdis #sjyouyaku](https://yamato-jp.org/wp-content/uploads/2016/09/b8136e229dc223db5126efaeaa5b7bce-150x150.gif)
2016/11/26付 北海道の地図を広げると、知床半島と根室半島のあいだの海に北方領土の国後島が深く入り込んでいる。近いとは知っていた。けれど実際に海岸線をたどれば国後はほんとうに目の前である...

昨日は勤労感謝の日で一応休日ということもあり 相方が「談山神社に高揚を見に行きたい」と言った。 談山神社は奈良県桜井市の多武峰にあって、桜と紅葉が有名。 中臣鎌足が祀られている。大化の改新の...
![[春秋要約161115]孤独に耐えられず、朴韓国大統領が利用された事件の政治空白は日本への影響も大きい。<40文字> #sjdis #sjyouyaku](https://yamato-jp.org/wp-content/uploads/2016/09/b8136e229dc223db5126efaeaa5b7bce-150x150.gif)
2016/11/15付 世界的な仏教学者、鈴木大拙は今年が没後50年だ。禅の世界を解説した著書によると、道場に入門を願う新来の僧は先輩から強い調子で断られ、時に力ずくで門外に出される。しかし、こ...
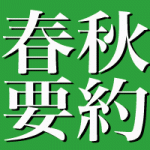
9月1日からスタートさせた日経新聞の春秋の要約は 元々、子どもの国語力+αを目的にしてはじめたのだが ついでに自分のブログのネタのひとつにも、とここまで続けてみた。 子どもには200文字への...
![[春秋要約161113]七五三では地域の産土神に詣で子供の成長の無事を願う。親心は今も昔も変わらない。<39文字> #sjdis #sjyouyaku](https://yamato-jp.org/wp-content/uploads/2016/09/b8136e229dc223db5126efaeaa5b7bce-150x150.gif)
2016/11/13付 そのとき、長年の謎が解けた。敦賀半島に残る出産のための小屋を調べて地元の人の話を聞くうち、ウブスナという言葉の語源をつきとめる。大家の柳田国男がどうしても分からないと嘆い...
![[春秋要約161111]次期トランプ大統領が現状打破の切り札か最悪の札か、市場も世界も見定めかねている。<40文字> #sjdis #sjyouyaku](https://yamato-jp.org/wp-content/uploads/2016/09/b8136e229dc223db5126efaeaa5b7bce-150x150.gif)
2016/11/11付 ドナルド・トランプ氏が米国の次期大統領に選ばれたことについて、シンガポールのリー・シェンロン首相がフェイスブックにコメントを投稿している。お祝いではじまり関係拡大への意欲...
![[春秋要約161030]少子高齢化が進み行く先の淵は深い。任期延長を目指す安倍首相は我々を導けるか。<38文字> #sjdis #sjyouyaku](https://yamato-jp.org/wp-content/uploads/2016/09/b8136e229dc223db5126efaeaa5b7bce-150x150.gif)
2016/10/30付 平均年収が約150万円、16歳以上の労働参加率は50%。そんな市が米ミシガン州にある、と本紙の国際面が伝えていた。フリント市である。ゼネラル・モーターズ(GM)発祥の地で...
![[春秋要約161028]戦争と平和を繰り返す人間の営みを、歴史家として見つめ続けた三笠宮崇仁さまが逝去。<40文字> #sjdis #sjyouyaku](https://yamato-jp.org/wp-content/uploads/2016/09/b8136e229dc223db5126efaeaa5b7bce-150x150.gif)
2016/10/28付 「言葉が通じなくても、踊りで心と心が通じ合えば、こんな愉快なことはないと思う」。百歳で逝去した三笠宮崇仁さまは、なにより人情味を大切にした。気さくで、いろんな集まりに顔を...
![[春秋要約161027]遡上する津波はまさかの極み。遺族の訴えは認められたが児童らを救えなかったものか。<40文字> #sjdis #sjyouyaku](https://yamato-jp.org/wp-content/uploads/2016/09/b8136e229dc223db5126efaeaa5b7bce-150x150.gif)
2016/10/27付 川という川が無残に荒らされた光景を、そのとき初めて見た。東日本大震災のあと、内陸から被災地への道で目に飛び込んできたのは河川の惨状だった。海の気配などまるで感じさせぬ上流...
![[春秋要約161024]道具の発明で効率優先になったが、機心に振り回されないよう気をつけないといけない。<40文字> #sjdis #sjyouyaku](https://yamato-jp.org/wp-content/uploads/2016/09/b8136e229dc223db5126efaeaa5b7bce-150x150.gif)
2016/10/24付 「なんと時代遅れな!」。孔子の愛弟子(まなでし)、子貢は驚いた。老人が井戸の中に入り甕で水をくんでいる。水を取り畑にまくなら、はね釣瓶(つるべ)という機械がある。声をかけ...
![[春秋要約161018]デフレ脱却黄信号にも関わらず配偶者控除廃止見送り。失われた歳月はいつまで続くか。<40文字> #sjdis #sjyouyaku](https://yamato-jp.org/wp-content/uploads/2016/09/b8136e229dc223db5126efaeaa5b7bce-150x150.gif)
2016/10/18付 多くの雲水が修行する曹洞宗の大本山、福井県の永平寺では11月末になると沢庵(たくあん)漬けを仕込む。使う大根は1万本以上。深さと直径が1.3メートルのおけに塩やぬかを敷き...
![[春秋要約161010]百貨店の閉店は「買い物」を取り巻く環境の急激な変化による小売業界の苦難の象徴だ。<40文字> #sjdis #sjyouyaku](https://yamato-jp.org/wp-content/uploads/2016/09/b8136e229dc223db5126efaeaa5b7bce-150x150.gif)
2016/10/10付 老夫婦とベテラン店員が心から別れを惜しんでいる。「またいつか、どこかでお会いしたいわね」と客の婦人。「ありがとうございます」と頭を下げる店員。先月末、千葉県で「そごう柏店...

ブログを書いていると 「文字を書くことが少しでも収入になれば一石二鳥なのに」と思ったり 「同じ書くならこれで食えたらなぁ」と思う人は少なくないだろう。 そういう自分も最近、クラウドワーク...
![[春秋要約161008]コロンビアの大統領がノーベル平和賞。ゲリラとの停戦状況のさらなる前進に期待。<38文字> #sjdis #sjyouyaku](https://yamato-jp.org/wp-content/uploads/2016/09/b8136e229dc223db5126efaeaa5b7bce-150x150.gif)
2016/10/8付 「ベネズエラの人たちはお金持ちだからね」。南米コロンビアの首都ボゴタをおとずれたとき、隣の国についてのこんな評価を耳にした。世界でもっとも原油埋蔵量が多いとされる国のオイル...
![[春秋要約161007]絶滅が心配されるウナギの取引実態が解明されないと、かば焼きが味わえなくなる。<38文字> #sjdis #sjyouyaku](https://yamato-jp.org/wp-content/uploads/2016/09/b8136e229dc223db5126efaeaa5b7bce-150x150.gif)
2016/10/7付 長寿を願い子どもにつけた名がもとで騒動が起きる落語の「寿(じゅ)限無(げむ)」。その長い長い名前の中の「海砂(かいじゃ)利(り)水魚(すいぎょ)」は、海の砂利や魚は取り尽く...
![[春秋要約161006]すぐに役立つ学問だけを重視する社会は、おもしろいヤツの居場所がなく薄っぺらだ。<39文字> #sjdis #sjyouyaku](https://yamato-jp.org/wp-content/uploads/2016/09/b8136e229dc223db5126efaeaa5b7bce-150x150.gif)
2016/10/6付 国立大に文系は要らない――。文部科学省が昨年、こう読み取れる通知を出したときに怒ったのは文系の先生たちばかりではなかった。日本学術会議のメンバーをはじめ、むしろ理系の学者、研究...
![[春秋要約161002]車離れが進む中、今後のヒット商品は自動運転車より「運転しにくい車」を予想する。<39文字> #sjdis #sjyouyaku](https://yamato-jp.org/wp-content/uploads/2016/09/b8136e229dc223db5126efaeaa5b7bce-150x150.gif)
2016/10/2付 先日、スポーツカーを買った。色は真っ赤。しかもマニュアル車である。注文の際、ディーラーの販売員に「いい年をして恥ずかしい」と言いわけをすると、「いや、僕が売った顧客のなかで...
![[春秋要約160925]魅力的な作品のロケ地観光で客を呼びつつ、マナーを守るなど地域への配慮も要る。<38文字> #sjdis #sjyouyaku](https://yamato-jp.org/wp-content/uploads/2016/09/b8136e229dc223db5126efaeaa5b7bce-150x150.gif)
2016/9/25付 映画「ローマの休日」に、女優オードリー・ヘップバーンが古い広場でイタリアの菓子であるジェラートを口にする印象的な場面がある。この広場を訪れ、同じようにジェラートを手にした観...
![[春秋要約160923]内戦に翻弄されるシリアの人々に寄り添い、我々はどんな「平和の哲学」を創るのか。<39文字> #sjdis #sjyouyaku](https://yamato-jp.org/wp-content/uploads/2016/09/b8136e229dc223db5126efaeaa5b7bce-150x150.gif)
2016/9/23付 明治後半から昭和初期の哲学者、西田幾多郎の著作は、難解なタイトルでいかにも近寄りがたい。しかし、その生涯に触れ、残された短歌を読めば、家庭人としての心労がしのばれて切ない。...